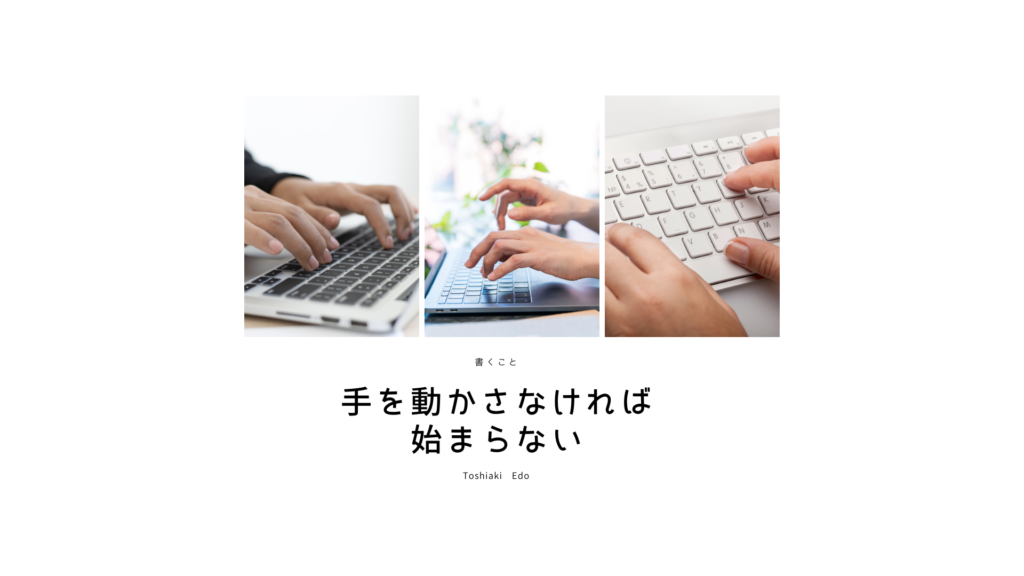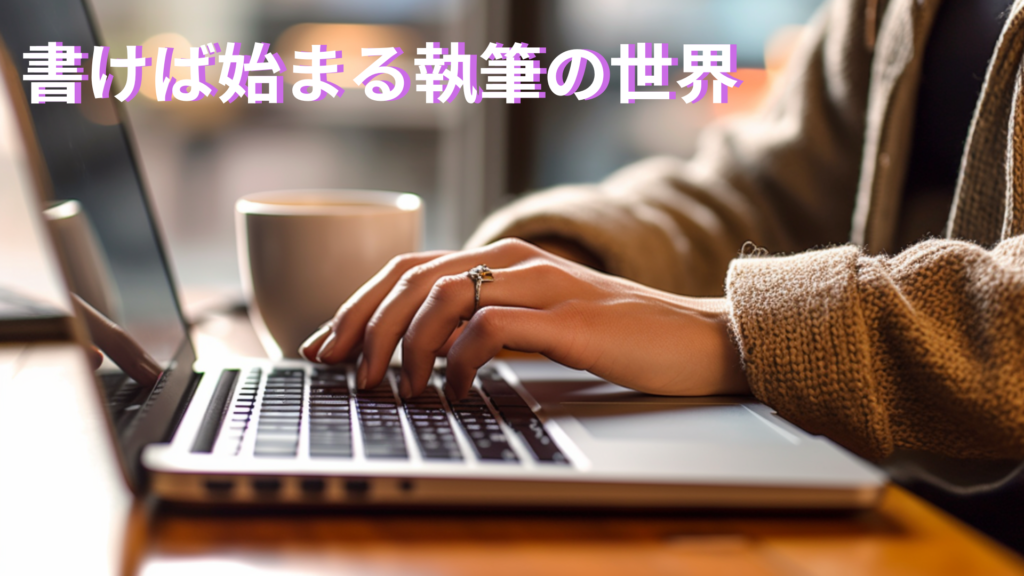ライターとして知っておくべきことを備忘録的に書き出しました。
ターゲットとなる読み手を明確にすること
読み手は誰?
相手はどんな人?
誰に向けた文章なの?
この辺が明確になっていると、伝えるべき情報が決まります。
文章も具体的になるので、相手の印象として残るでしょう。相手が自分事として受け入れられるかは、相手の求める具体的なニーズと合致させること。合致できれば印象的な文章になり、強く伝わります。
記事の目的を明確にすること
目的を明確にすることは、文章の方向性、コンテンツの意義を示すために重要な準備です。ターゲットが定まっていれば、読み手目線のシナリオが組み立てられます。
「この記事を読む前の相手はどのような状態なのだろうか」
「この記事を読み終えたときに相手はどのような状態になっているのか(なってほしい)」
相手になってほしい状態こそ、記事の目的です。目的を決めると次の効果が期待できます。
- 目的に向かって書くべきことを明確にできる
- 目的とは関係ない欠く必要のないことが明確になる
- 目的に適した文章の構成が組み立てられる
- 目的に適したトーン(口調・文体など)を決められる
- 目的に適した書き方で取り組める
クライアントから共有されるレギュレーションの重要性
クライアントから共有されるレギュレーションは、仕事をするうえで欠かせない指標です。住宅の建築で例えた場合、家の設計図を作成する際の顧客の要望とも言えます。
顧客の要望は、ときとして業界の常識から逸脱した内容かもしれません。もしくは、業界の裏事情を汲み取って決めていることも考えられます。
レギュレーションは、必ずしも記者ハンドブックや正しい日本語表記であるとは限りません。そこには、相手の事情(読み手への配慮・目的)などが含まれます。クライアントが共有するレギュレーションは、記事の方向性を加味した執筆ガイドラインとなるのです。
具体的にレギュレーションは、次の点についての統一指標となるでしょう。
- 文章の書き方
- 文章の表現方法
- 文章の表記についての共通認識
これらを統一させることでクライアントの意向を理解した書き手になれるわけです。
レギュレーション例
- 誰がターゲットとなるのか
- 何を伝える文章なのか(どんな目的に向けた文章なのか)
- どの媒体に掲載される記事なのか
- 媒体や記事のコンセプトは何か
- 文体は何で統一させるか(ですます調など)
- トーン&マナー(略してトンマナ:文章表現・画像・色・デザイン・スタイルなど)
レギュレーションは、細かいクライアントもいれば、重要な部分だけ示してあとはライター任せなクライアントもいます。記事の表記などは、次の表記統一が求められるでしょう。
- 数字(全角・半角・西洋・漢字など)
- アルファベット(全角・半角など)
- 記号(使用可能・使用不可など)
- 略語表記
- 引用文の表記
- よく使う単語の表記(カタカナ・漢字・ひらがな表記)
正確な情報源(リソース)と正しい表記で書く
記事の責任は、意外と重いです。ましてビジネス系の記事となれば企業の評判にも影響します。そのため、ライターは正確な情報源(リソース)と正しい表記で執筆することが重要です。
- 情報:正しい情報(公式サイト・公的機関・一次情報・有識者の発言など)
- 表記:表記ミスのない記述
正しい情報を得るための方法では、該当者へのヒアリング・取材なども考えられます。出版されている関連書籍や関連Webサイトの場合は、情報の正確性を再度精査したうえで利用することも必要です。
情報源の正確さは、専門性や権威性にも左右されます。参考情報が正しければ、読者の信頼も得られるでしょう。執筆者自身の見解や思惑で書いた記事では、後日専門家のチェックにより淘汰される可能性があります。
参考情報の正確性をチェックする
参考情報の正確性をチェックするには、情報発信元の見極めスキルを高めましょう。情報の出処として専門性や権威性が担保できる発信元は、次のとおりです。
- 公的機関
- 国が発信する情報
- 出典企業
これらは、客観的に専門性や権威性を訴求できる発信元として取り上げました。あくまでも客観的な捉え方です。ただし、公的機関でも間違った情報を発信することも考えられます。また、情報が古くなっていたり更新していなかったりする場合もあります。情報の発信時期なども注意深くチェックすることが重要です。
主体は独自コンテンツ
正しい情報を参考にして書くことは、重要なことですが丸パクりではコピーコンテンツになるでしょう。主体は、独自コンテンツの作成です。参考情報を適所に設置し、読者の信頼を担保しながら独自の視点も埋め込んでいくとオリジナル性が担保できます。
たとえば、公的機関が発信する法改正の情報に対して、記事のターゲットとなる読者目線で具体的な活用例を組み込むだけでもオリジナル要素は高くなるでしょう。
働き方改革についての説明の場合は、読者層が経営層であれば使用者として法改正についてどのような注意が必要か?という点に着目します。読者にとって身近な活用例があれば、「自分事」として捉えてもらえます。
著作権
ウェブ上で公開されている情報には、著作権があるものも多数存在ます。企業や個人のウェブサイトでは、ページの最下部に「掲載情報の取り扱い」について注意している場合もあるでしょう。うっかり情報を再利用した場合、著作権侵害などで訴えられるかもしれません。
著作権は、執筆に携わるすべてのライターにとって周知しなければならないルールです。
- コピーアンドペーストはNG
- 引用に関しての取り扱いを確認する
- 引用可能な情報を正しく取り扱う(引用元・出典元など出処の明示)
- 情報元企業や個人の意思に反しないこと
正しい日本語で正しく伝える
正しい日本語で伝えるには、文章で使う言葉の表現と会話で使う言葉の表現の違いについて理解が必要です。
| 書き言葉と話し言葉の区別 | |
| 書き言葉 | 話し言葉 |
| やはり | やっぱり |
| とても | とっても |
| そちら | そっち |
| なぜ | なんで |
| きちんと | ちゃんと |
| さきほど | さっき |
| さらに | もっと |
| ようやく | やっと |
記事で表現する(ビジネス目的)場合は、書き言葉を意識することが必要です。
文章を校正しよう
文章の校正では、誤字脱字のチェックが大事です。誤字脱字のチェックは、ツールでもできますが、自己チェックが強力ではないでしょうか。ツールによる誤字脱字チェックは、見落としがちになることもあります。
とくに、声に出して読むことが効果的です。徹底的に誤字脱字をチェックする場合は、プリントアウトもひとつの方法。プリントする手間に対して使命感も湧いてきます。
さらに、チェック作業は時間を空けることで着眼点も変わります。そのため、視点を変えたチェックができ誤字脱字が発見しやすくなるでしょう。
また、時間を空けての再チェックは表記ゆれの発見にも役立ちます。記事執筆にあたりクライアントの作成したレギュレーションなどがあれば、それらをチェックリストにして使う方法も有効です。
中には、有料や無料の文章校正ツールも利用できます。たとえば、次のツールなどです。
文章校正に役立つツール
| 有料の文章推敲校正ツール | 無料の文章校正ツール |
| 文賢
※広告に移動します。 記者ハンドブック第14版新聞用字用語集の内容を網羅 |
テキスト処理ツール「文章校正」 |
読みやすい文章を考察
読みやすい文章を作成する意義は、「見てくれ」「ファーストインプレッション」にあります。要するに、第一印象を良くしてそのまま読み進めてもらうという狙いです。
読みやすい文章は、読みにくい文章とは逆の工夫が必要になるでしょう。
| 読みやすい文章 | 読みにくい文章 |
| 適度に空白行や改行が入っている | 大量の文字がぎっしり詰まっている |
| 漢字やひらがな、カタカナ、英数字などをほど良く使っている | カタカナ表記の長文 |
| 画数が少なくそのままの流れでも理解できる漢字を使う
【例】
|
画数が多く調べないと読めない漢字を使う
【例】
|
| テンポよくスラスラ読める | いちいち確認しながら読まなければならない |
| テーマごとに区分されている | ひとつの文章の中で複数のテーマが混在している |
読みやすい文章は、テーマごとに分けられています。テーマが絞られた文章は、そのテーマの情報だけに集中できます。このテーマを絞る点で重要な役割となるのが見出しや階層構造です。
見出し
見出しは、文章を大きなテーマから小さなテーマに細分化し階層構造で構成するために必要な文中タイトルです。たとえば、次のような文章があるとしましょう。
Windows ショートカット
- Win + V:コピー履歴の呼び出し
- ctrl + shift + T :消したTabの復活
- ctrl + shift + ESC:タスクマネージャの呼び出し
- Win + G:画面録画
- Win +Alt + Prt sc:キャプチャ
- Win + ← → ↑ ↓:画像分割
参考になれば幸いです。